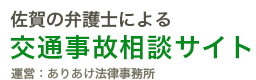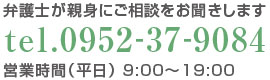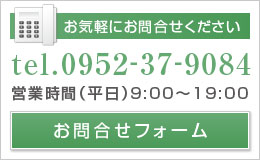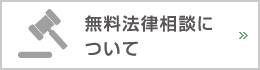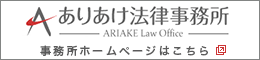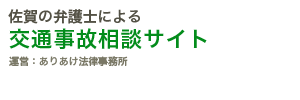Archive for the ‘未分類’ Category
<弁護士交通事故裁判例>両足運動麻痺の被害者に対し補装具購入費等を認めた事例
補装具購入費 94万2367円(被害者側主張額 183万3760円)
被害者は後遺障害のため車椅子および長下肢装具を5年毎に合計7回買い替える必要がある。
なお、被害者は将来購入する補装具の価格は消費者価格の上昇により現在の価格を上回ることが明らかであるとして、その損害額の現価を算出するに当たり、中間利息を控除すべきでないと主張するが、将来長期間にわたり毎年継続して消費物価が法定利率の年5年分を超える割合で上昇するものと認める確実な証拠はないから、この主張はたやすく採用することはできない。
乗用車改造費 38万4427円(被害者側主張額 78万4000円)
被害者が今後も自動車を運転するためには、後遺障害のある被害者にも運転し得るように改造が必要であり、自動車の耐久年数が6年とされていることから、平均余命まで以後6年毎に合計6回の改造を要する。なお、中間利息を控除すべきでないとする被害者側の主張は、補装具購入費に判示したところと同様に認められない。
(東京地裁昭和60年5月10日判決)
<弁護士交通事故裁判例>身体障害者用ベッドの購入費用の賠償を認めた事例
身体障害者用ベッド 53万4000円(被害者の主張どおり)
被害者は本件事故により被った後遺障害のため、日常生活を営むに当たって身体障害者用ベッド一式を要する状況になっていたことが認められる。
ホイスト・車椅子 0円(被害者側主張額 72万円)
損害を認めるに足りる証拠はない。
(東京地裁昭和59年7月27日判決)
<弁護士交通事故裁判例>症状固定後の治療費につき平均余命まで認めた事例
被害者の後遺障害の内容・程度、治療経過およびA病院整形外科担当医の「今後増悪の可能性がありアフターケアを要する」との見解や、同病院泌尿器科担当医の「永久に自己導尿が必要であると考える」との見解を考慮すれば、被害者については、症状固定後も、平均余命に至るまで、症状の増悪防止および排尿管理のため、A病院整形外科および同泌尿器科を継続的に受診する必要性・相当性が認められ、これに係る治療費および薬剤費を支出する蓋然性が認められるというべきである。被害者は、症状固定日の翌日である平成22年8月3日~平成24年6月2日の22か月間で、A病院整形外科および同泌尿器科における治療費および薬剤費として、合計18万1440円を支出したと認められる。被害者は、症状固定後、A病院整形外科および同泌尿器科における治療費および薬剤費として、月額8247円を支出する蓋然性が認められるというべきである。被害者は症状固定時52歳であり、平成22年の簡易生命表によると52歳男性の平均余命は29.71歳であるから、症状固定後の治療費が発生する期間は、症状固定時から29年間と認めるのが相当である。
(東京地裁平成26年12月24日判決)
<弁護士交通事故裁判例>泌尿器科の将来治療費を認めた事例
被害者に排便・排尿障害が生じていることは主訴を経ずとも明らかであり、またその症状について医学的な説明も一定程度可能なものといえ、相当因果関係も肯定される。泌尿器科に関する将来治療費の年額8610円については、今後症状が解消する見込みがない以上、将来にわたって必要となるものと認められ、相当性が認められる。将来治療費については、泌尿器科に関する年額8610円の範囲で本件と相当因果関係のある損害と認められ、これについて被害者が主張するライプニッツ係数13.7986を乗じると11万8806円となる。
被害者の主張によれば、泌尿器科への通院は2か月に一度であるいうところ、1回当たりの往復交通費1810円は証拠および弁論の全趣旨により相当なものと認められ、年間6回分である1万860円にライプニッツ係数13.7986を乗じると、14万9853円となる。
(大阪地裁平成25年8月27日判決)
<弁護士交通事故裁判例>将来の入院費を平均余命にわたり認めた事例
被害者は、本件事故による慢性硬膜下水腫のため、高次脳機能障害の後遺障害を負ったところ、見当識が著しく障害されており、注意障害や徘徊が認められ、閉鎖病棟による管理を要する状況にあることが認められる。被害者については、症状固定後もなお入院の必要性・相当性があるものと認められ、個室によることもやむを得なかったものと認められる。証拠および弁論の全趣旨によれば、症状固定後の平成25年7月までは、国民健康保険限度額適用認定証により自己負担額の減額を受け、1か月当たりの入院費の負担は12万と見込まれること、平成22年8月以降、1年ごとに認定証の申請を行ってその交付を受けており、70歳までは交付を受けられる蓋然性があること、70歳以降も、国民健康保険法または高齢者の医療の確保に関する法律における同様の限度制度に基づき、上記認定証と同様の自己負担額の減額を受けられる蓋然性があることが認められる。被害者の将来入院費は、1か月当たり12万円を基礎として、症状固定時62歳男子の平均余命21年間にわたり要するものと認められる。
(東京地裁平成25年8月6日判決)
<弁護士交通事故裁判例>症状固定後の治療費につき月額50万円を認めた事例
被害者には1級1号に相当する後遺障害が残存していることより、相当な範囲においては、将来の治療費を損害として認めるべきである。症状固定後の治療費のうち、金額が具体化していない将来の治療費の額については、被害者が、現実に治療費として自ら負担している部分を前提に想定される範囲にとどまらず、社会保険からの給付を含めた治療費全額を賠償の対象とすることが相当である。
口頭弁論終結時(平成22年11月)
現実に支出した金額にとどめて賠償額を定めることが相当である
口頭弁論終結後
諸般の事情を勘案すれば、月額50万円とみるのが相当である。口頭弁論終結時の被害者の年齢77歳の平均余命より13年間の範囲で賠償が認められるべきである。
(大阪地裁平成23年4月25日判決)
<弁護士交通事故裁判例>将来の人工股関節置換手術の費用を認めた事例
証拠によれば、被害者は本件事故の骨盤骨折により関節内の軟骨が毀損しており、今後残存した軟骨も摩耗して人工股関節置換手術の可能性が高いこと、人工股関節置換手術による人工股関節置換の耐久年数は約20年であることから、被害者について今後少なくとも2回は同手術の必要があると考えられることが認められる。また、弁論の全趣旨に照らせば、同手術の費用は、1回に200万円を要するものと認められる。以上を前提とすれば、被害者が症状固定時25歳であってその平均余命や、前記のとおり少なくとも2回の手術が必要であることを勘案すれば、被害者は、40歳(症状固定から15年後)に至った時点と、それから20年後である60歳(症状固定から35年後)に至った時点の2回人工股関節置換手術が必要となる蓋然性が高いというべきである。
(大阪地裁平成22年1月27日判決)
<弁護士交通事故裁判例>将来の治療費を44年にわたり認めた事例
被害者は、右下肢の皮膚機能の低下等があり、保湿機能を高めて乾燥を予防するため、保護クリームを生涯にわたって常用する必要があること、そのための治療費は、診察料1020円および薬代680円の合計月額1700円であることが認められる。
(東京地裁平成21年11月16日判決)
<弁護士交通事故裁判例>将来治療費を平均余命まで認めた事例
1回当たりの診察費は3600円であり、リハビリ費は2370円であるところ、今後平均余命までの間、月1回の診察と週2回程度のリハビリを要することから、将来の治療費として382万9866円が必要というべきである。
(大阪地裁平成21年8月25日判決)
<弁護士交通事故裁判例>将来の訪問看護及びリハビリ費用を平均余命まで認めた事例
被害者は、現在リハビリのために週3回の訪問看護に加え、平成19年月からは週1回の訪問リハビリを受けていること、平成18年9月~平成19年4月までの訪問看護費の月平均は、2万6841円であることが認められる。もっとも、被害者らは、別途職業介護人による介護を含めた将来の付添看護費等を請求していることも勘案すると、被害者について、本件事故との相当因果関係を認めることができる訪問看護は、週3回であると考える。被害者は、上記に加え、リハビリの必要性を主張するが、今後被害者に対し、いかなるリハビリが行われるのかについてはなお不明であるから、被害者主張の訪問リハビリが今後平均余命まで必要であり、これが本件事故と相当因果関係のある損害に当たるとまでは即断できない。本件に現れた諸般の事情を考慮すれば、訪問介護費及び訪問リハビリ費用として加害者側が負担することが相当な額は、月額3万円と認める。
(大阪地裁平成21年1月28日判決)
« Older Entries Newer Entries »