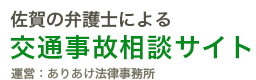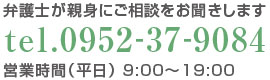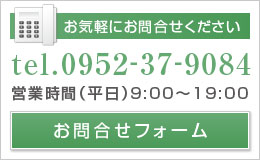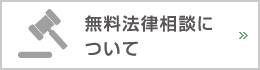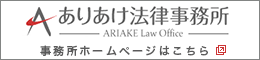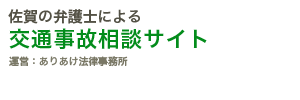Archive for the ‘未分類’ Category
<弁護士交通事故裁判例>バスと電車の通勤交通費を認めた事例
被害者は、本件事故前は自転車を使って通勤していたところ、本件事故により右鎖骨骨折の傷害を負い、自転車の運転が一時的に不可能となったため、鎖骨骨折が完治して再び自転車の運転が可能となるまでの間、バスと電車を使用する形での通勤方法および経路を変更せざるを得なくなったこと、これに伴い、被害者は、片道530円の交通費を余計に支出せざるを得なくなったところ、この交通費を要したのは13.5日分であることが認められる。
被害者は、実況見分への立合いおよび警察署に保管されていた自転車の引取り、警察署への診断書の提出、警察署での被害者供述調書の作成に合計4950円の交通費を要したことが認められる。捜査に協力するのは国民の義務ではあるが、被害者が該当義務を負担するに至ったのは、本件事故によるものであるから、上記交通費合計4950円は、本件事故と相当因果関係のある損害と認められる。
(東京地裁平成24年12月21日判決)
<弁護士交通事故裁判例>通院につきタクシー利用を認めた事例
被害者側は、退院後から症状固定前(約8か月間)に被害者および妻が必要とした交通費として、タクシー代およびバス代等10万7110円を請求する。被害者の後遺症の程度(バランスが悪く長距離の歩行が困難であること等)、妻の年齢および妻が変形性膝関節症を患っていることに照らすと、通院等の際に、タクシーを利用することもやむを得ないと認められ、被害者が必要としたタクシー代を損害として認める。被害者の後遺症の程度や妻の状態に照らすと、被害者がバスを利用した際には、妻の負担が特に重かったといえる。したがって、退院後の期間については、妻のバス等利用の交通費も介護(退院後症状固定前)の評価とは別途、認める。
被害者の子が本件事故後、被害者の見舞いに訪れているが、遠方に居住していたことから、飛行機代およびタクシー代等が発生しており、これを損害と認める。
(大阪地裁平成24年5月16日判決)
<弁護士交通事故裁判例>就職活動のための交通費を認めた事例
被害者は本件事故による後遺障害の影響により、本件事故当時の職業であった大工の仕事を継続するのは不可能であり、新たな職業を探す必要があったと認められるから、就職活動のための交通費3万2440円は本件事故との間に相当因果関係のある損害と認められる。
(東京地裁平成22年2月17日判決)
<弁護士交通事故裁判例>将来介護費を日額3000円で平均余命まで認めた事例
被害者は、本件事故により、びまん性脳損傷、右肩胛骨骨折等の傷害を負い、併合4級の認定を受けたこと、日常生活動作は自立しているものの、記憶障害、持続力、集中力、問題解決能力が著しく低下し、活動力の低下、感情易変、易怒性、暴言、暴力などが見られること、そのため、日常生活動作を行うにしろ、母および妻が見守り、声がけ、援助をするなどしなければならず、外出についても一人ではできず、付添が必要なこと、このような状況は、本件事故後約4年近く経過した現在でも変化はないことなどが認められる。これらのことからすれば、被害者については、随時見守り、声がけ、付添等が必要であり、これまでの経過からすると、被害者の平均余命46年にわたって継続するものというべきである。このような状況からすると、将来介護費としては日額3000円を認めるのが相当である。
(神戸地裁平成26年9月24日判決)
<弁護士交通事故裁判例>介護施設に入居した被害者について将来介護費を認めた事例
被害者は、平成23年11月15日(当時80歳)以降介護施設に入居していること、入居一時金として、家賃相当額の1788万と介護サービス料等に相当する生活支援費308万4000円支出したこと、入居後は、食費や水道光熱費のほかに毎月、事務費、管理費等に充てられる管理費10万5000円、おむつ代1万2180円、マッサージ代2400円、介護保険10%負担金2万6540円の合計14万6120円を要していることが認められる。これらの費用のうち、生活支援費308万4000円、月額14万6120円は介護費用と認められる。家賃相当額1788万については70%の限度で介護費用を認めるのが相当である。
(神戸地裁平成20年4月30日判決)
<弁護士交通事故裁判例>将来の介護料を日額1万円で28年間認めた事例
被害者は、本件事故当時一人暮らしであったが、事故後、知人が身の回りの世話をしたり、買物に行くなどしていたことが認められる。しかし、知人が被害者を常時介護していた事実を認めるに足りる証拠はなく、また、事故直後に四肢の麻痺および筋力の低下が生じていた事実も認められないから、事故直後から介護の必要があったとは認められない。被害者は平成17年3月22日から通院を中断後、徐々に四肢の麻痺および筋力の低下等が認められ、身体障害者福祉法における2級相当と診断されたことからすれば、症状固定日までの間の1009日について、介護者が近親者ではないことからすると、日額1万円の介護費用を認めるのが相当である。
被害者の現在症状の程度に鑑み、症状固定日から28年間、職業介護人による介護を前提としても、日額一万円の限度でこれを認めるのが相当である。
(東京地裁平成26年1月16日判決)
<弁護士交通事故裁判例>将来の介護料を日額3000円で平均余命まで認めた事例
1631万3310円
被害者は、一定程度の生活は送れる状況であり、常時介護を必要とするわけではないが、外出時に家事を行う時、入浴時あるいは階段の昇降等の場面において、一定の介助や見守り等を必要とするものと認められ、将来介護の必要性は認められる。その症状内容に照らすと、今後職業付添人が必要となる蓋然性については認められないが、将来にわたって近親者による介護に必要があり、日額3000円相当の損害が発生しているものと認められる。
3000円×365×14.898(平均余命28年のライプニッツ係数)=1631万3310円
(大阪地裁平成25年9月26日判決)
<弁護士交通事故裁判例>将来の介護料を定期金賠償で認めた事例
被害者は、将来請求については定期金賠償の方法によるべきことを強く希望していることに加え、将来介護費等は将来にわたって定期的に支出を要する費用であり、被害者の年齢に照らし、その介護期間は相当長期に及ぶことが予想され、定期金賠償による賠償方法になじみやすいことを考慮すると、これらの賠償については、定期金賠償により賠償することを命じるのが相当であると解される。被害者の介護の必要性およびその程度を前提とし、今後将来の同人の成長、導尿等の習熟等を総合考慮し、症状固定日の翌日から母親が67歳に達する日までは、1日8000円として月額24万円、その後被害者が死亡するまでは、職業付添人による介護を想定し、1日1万5000円として月額45万円を損害として認める。なお、本件口頭弁論終結日の前月までの分は、いわゆる将来請求ではないから、一時金として認めるのが相当であると解される。
(福岡地裁平成25年7月4日判決)
<弁護士交通事故裁判例>将来介護費を平均余命まで日額8000円で認めた事例
被害者の状態及び医師の意見に照らすと,今直ちに在宅介護は困難であるものの,将来態勢を整備した上での在宅介護が不可能とまでは認められず,かかる前提として算定することとする。平均余命まで日額8000円の将来介護料を認めるのが相当である。
(名古屋地裁平成24年10月26日判決)
<弁護士交通事故裁判例>ガーゼ取り換えのための自宅介護費用を認めた事例
被害者は,皮膚移植をしたため,自宅においても,本人の手の届かない部分にも1日数回のガーゼの取替えが必要であり,1177日間付添看護の必要があったといえるが,その看護の内容程度に照らせば,付添看護費は日額2000円とするのが相当であり,本件事故と相当因果関係のある自宅付添看護費は合計235万4000円と認めるのが相当である。
(大阪地裁平成24年7月30日判決)
« Older Entries Newer Entries »