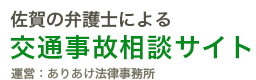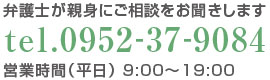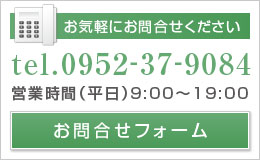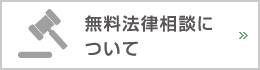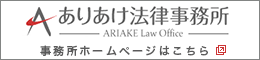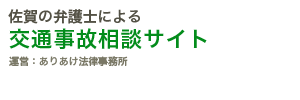Archive for the ‘未分類’ Category
<弁護士交通事故裁判例>会社役員の休業について会社が役員報酬を肩代わりした損害を認定した事例
生活態様:被害者は飲食業等を目的とするA社の取締役であり,A社が
経営する飲食店で店長兼バーテンダーとして働いている。接
客および酒食の提供をしているが,店で出す料理も被害者が
作っている。
算定基礎:年額¥7,200,000
被害者の役員報酬¥9,000,000のうちの労務対価部分
休業日数:79日
被害者が本件事故による傷害のため休業した日数
認容額:¥1,558,356
(横浜地裁 平成24年12月20日判決)
<弁護士交通事故裁判例>会社代表者の受傷につき会社損害として役員報酬を基に598日間に20%の休業があったとして認めた事例
生活態様:建築会社の代表者で重い建築部材などを運びながら住宅の骨
組みを建築していた。
算定基礎:年額¥4,800,000
事故当時の役員報酬の額
休業日数:119.6日
本件事故後1週間以内の時期においても現場監督の仕事をし
ていること,被害者の最も重要な仕事は現場で仕事の指示を
することなどから,事故日から症状固定日までの598日間
について20%の休業があったものとする。
認容額:¥1,572,822
(名古屋地裁 平成23年7月15日判決)
<弁護士交通事故裁判例>65歳代表取締役の休業損害について賃金センサス男子大卒65歳以上平均賃金をもとに認めた事例
生活態様:被害者は,弁護士名簿登録取消後会社に入社,代表取締役
就任後は,主に会社を当事者とする各種訴訟手続等において,
自ら書面を作成し,法廷等に出頭する等していた。
算定基礎:年額¥7,084,000
被害者が会社から支給を受けていた金員は代表取締役として
の報酬であり,会社を当事者とする各種訴訟手続等を行う
業務に対する対価が含まれているとみるのが相当であり,
弁護士報酬相当額の損害を別途計上することはできないと
いうべきである。
休業期間:107日
被害者はH16.10.27からH17.2.10までの
107日間,会社を休業したことが認められ,上記の休業は,
被害者の障害の内容及びその治療経過に鑑み,本件事故と相当
因果関係のあるものと認められる。
許容額:¥2,076,679
(大阪地裁 平成19年10月30日判決)
<弁護士交通事故裁判例>鳶工事業有限会社代表者かつ鳶職人である被害者の休業損害について,労働対価部分を給与の65%と認めた事例
生活態様:被害者は本件事故前,有限会社の代表取締役として同社から年額
¥11,280,000の給与を得ていたところ,自ら現場監督
および鳶職人として稼働していた。
算定基礎:¥7,332,000(日額¥20,087)
被害者は平成15年6月に仕事を復帰後も本件事故により現場監督
および鳶職としての稼働が不可能になったため,給与が年額
¥7,800,000に減額していることなどを考え併せれば,
その労働の対価部分は給与の65%とするのが相当
休業日数:193日+92日X45%
入通院日数の合計の193日については,労働能力喪失率100%,
固定日までのその余の日数92日については,後遺障害等級8級相当
の45%と考えるのが相当である。
認容額: ¥4,708,392
(東京地裁 平成18年5月26日判決)
<弁護士交通事故裁判例>親族経営の印刷会社の役員につき、会社規模および労働実態から、実際の報酬¥1,300,000のうち労働対価性のある部分は¥910,000を下らないと認定した事例
生活態様:被害者は経営者と親族関係にある印刷会社の役員をしていた。被害者は実質的な
営業活動をしており、名目的取締役に留まらない。事故前は月額¥1,300,
000(年額¥15,600,000)の収入を得ていた。
算定基礎:月額¥910,000
被害者が役員をしていた印刷会社の保管の役員の報酬や従業員の給与およびこれら
の職務内容は必ずしも明確ではないし、被害者は印刷会社の経営者と親族関係にあ
るから、役員報酬中に労働対価性に欠ける利益配当部分(実質的利益配当部分や情
誼に基づく部分等)が含まれていることは否定できない。しかし、印刷会社の規模、
利益状況に加え、被害者が実質的な営業活動をしており、名目的取締役に留まらな
いこと、事故後の役員報酬のうち労務対価性のある部分は、事故前の月額¥
1,300,000(年額¥15,600,000)の70%である月額¥
910,000を下らない。
休業日数:18か月
認容額 :¥7,380,000
(東京地裁 平成17年1月17日判決)
<弁護士交通事故裁判例>会社役員の休業損害について役員報酬年額¥8,100,000の全てを労働の対価として休業損害を認めた事例
生活態様:資本金¥10,000,000、従業員39名で、貨物運送部門とクレーン建設
部門を有する会社で作業現場に出て、現場監督を行ったり、クレーンの操作等の
作業を行っていた。会社で2級土木施工管理士の有資格者は被害者のみである。
算定基礎:年額¥8,100,000
被害者はH13.7頃、取締役となっていた祖母の死亡により後任の取締役に
就任したが、取締役就任後も被害者の勤務内容、勤務時間等に変化はなく、取締
役としての報酬額も従前給与として支給されていた金額と同等であるなど、実質
は従業員として勤務していたと解され、被害者に支給されていた報酬は、すべて
労働の対価であったと解するのが相当である。
休業日数:5か月
認容額 :¥3,300,000
会社は年度途中での報酬の増減ンは税務処理上煩雑となるため、事故日以降も被
害者に対して減額することなく支給し、次年度において休業期間5か月分に相当
する¥3,300,000を減額したため、本件事故による休業損害は
¥3,300,000と認められる。
(名古屋地裁 平成16年4月23日判決)
<弁護士交通事故裁判例>会社役員の休業損害につき受領金額から利益供与分を控除した残額を労務の対価として算定基礎にした事例
生活態様:医療機器販売会社の代表取締役
算定基礎:¥6,774,400(年額)、¥34,794(日額)
被害者は、本件事故当時、役員報酬としてY商会から月額¥1,700,000
(年額¥20,400,000)を受領していたが、本件事故後、H6.3から
H6.8までの間無報酬となり、H6.9からH7.2までの間役員報酬が¥
1,000,000となったことが認められる。しかし、Y商会が本件事故で
負傷した被害者の稼働困難による経常損失を計上した第15期(H6.4.1
からH7.3.31まで)においてもなお被害者に¥7,700,000の役員
報酬を与えていることを考慮すると、同報酬額相当額は被害者に対する利益供与
と評価することができ、被害者の役員報酬中労務の対価と評価することができる
のは、これを控除した残額、すなわち年収¥12,700,000であり、これ
をもって、稼働すれば得たであろう利益を算定するための基礎収入とするのが
合理的である。
被害者は入院期間中にも現に取引先と交渉したり営業担当者との意思疎通を図っ
ていたので、同期間中(144日)は80%の休業の実態とその必要があったも
のとして、その余の通院期間中(266日)は40%のそれがあったものとして
算定するのが相当である。
休業日数:入院期間である144日と通院期間である226日の合計370日
認容額 :¥7,153,646
(東京地裁 平成13年5月30日判決)
<弁護士交通事故裁判例>パン屋個人営業の被害者の休業損害算定につき、役員報酬の月¥500,000は全額労務提供の対価としてみるべきとして、基礎月収を月額¥500,000とし症状固定時まで100%の労働能力を喪失したと認めた事例
生活態様:S61頃から個人営業のパン屋を営んでいたが、H6.9.9、、同所に
おいてパン・菓子の製造販売等を目的とする有限会社を設立して自らが代表
取締役、被害者の妻が取締役となって、以後は常時パート従業員12,3名
を雇い、会社組織でパンの製造販売を行ってきた。被害者は個人営業の時代
から会社組織とした後も、一貫してパン製造職人として働いてきた者であり
妻やパート従業員に補助的作業をさせることはあっても、熟練を要するパン
の製造工程の中心的部分については専ら一人で担当してきた反面、会社の
経理面に関しては妻および税理士に任せきりにしていた。
算定基礎:月額¥500,000
事故当時被害者が役員報酬として得ていた月額¥500,000の収入は、
利益配分としての性格をもつものとは言えず、全額これを労務提供の対価と
見るのが相当というべきである。
家賃収入として申告していた月額¥300,000の収入については、労務
提供の対価とみることは困難であるといわざるを得ない。
休業日数:19か月
被害者の障害の程度や会社において本件事故以前に被害者が担当していた
労務内容、本件事故以後の業務への関心の程度、会社において本件事故後、
売上総利益が明らかに減少する反面、営業損失が増加していること等に照ら
せば、症状固定時までの19か月間、100%労働能力を喪失したものと
して算定するのが相当である。
認容額 :¥9,500,000
(大阪地裁 平成12年9月7日判決)
<弁護士交通事故裁判例>コンピュータソフトの企画・製作を業務とする会社の代表者の休業損害認定例
生活態様:被害者は、コンピュータゲームソフトの企画・制作を業務とする従業員10名
アルバイト10名程度の小規模な会社の代表者で、事故当時会社の交渉、企画
管理の全般にわたり現実に労務を提供しており、被害者の交渉能力、ゲームソ
フト開発のための専門的な知識・技能が会社の営業に不可欠なものであった。
そのため、役員報酬に占める労働対価部分は7割を下ることがない。
算定基礎:日額¥42,140
(事故当時の役員報酬月額¥1,444,825の70%)
休業日数:22.5日間(4日+34日☓0.5+5日☓0.3)
事故当時の欠勤は100%、その後の通院は50%、その余の欠勤・通勤は
30%の割合で休業損害を認定する。
認容額 :¥948,150
(東京地裁 平成11年10月1日判決)
<弁護士交通事故裁判例>代表取締役の休業損害につき、役員報酬の80%を労働の対価と認めた事例
生活態様:代表取締役
S60に設立された会社の常勤の代表取締役
従業員は70名でパートタイマーを含めると120名
被害者は、会社設立当時から経営の中枢におり、資金調達や建物の建築など
重要な事柄について決定することなどの仕事に従事していた。
算定基礎:年収¥12,704,867
H6の収入の8割を実際の稼働による対価とするのが相当
休業日数:54日+403日☓0.5+336日☓0.25
H6.7.31からH6.9.15までの入院47日とH7.6.22から
H7.6.28までの入院7日をあわせた54日は100%、H6.9.16
からH7.10.30までの内入院を差し引いた403日については平均して
50%、H7.10.31からH8.9.30まで336日については平均し
て25%の限度で労働能力を制限されていたと判断
認容額:¥11,799,862
(東京地裁 平成10年9月21日判決)
« Older Entries Newer Entries »