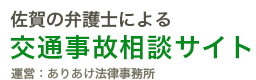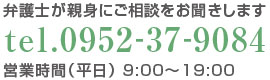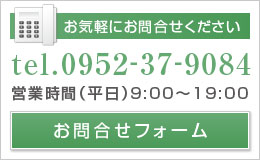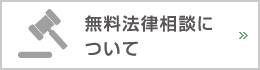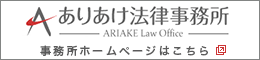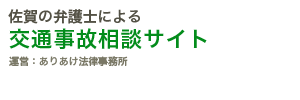Archive for the ‘未分類’ Category
<弁護士交通事故裁判例>介護設備工事としての費用の65%で認定した事例
家屋改造費:907万4000円
車椅子の移動スペースの必要性等を考慮すると、被害者の介護のために居宅を新築することについて、必要性および相当性が認められるが、新居宅の被害者の介護のためのスペースの面積全てが必要であったとは認められず、面積の対比等を総合考慮し、介護施設工事費用(エレベーター費用を除く。)の65%である907万4000円を加害者側に負担させるのが相当である。
車両購入費用:240万円
被害者のために新たに大きい自家用乗用自動車を購入する必要性があり、新車両と旧車両の差額分が本件事故と相当因果関係のある損害となる。改造費用111万3500円および車両購入費の増加分の損害として新車両の価格の約40%の合計額である240万円の程度で相当と認める。
将来の車両改造費:161万5911円
改造費用は本件事故と相当因果関係があり、その買換は、10年ごとに必要となるので被害者の平均余命まで5回の買換を要する。
(大阪地裁平成24年7月25日判決)
<弁護士交通事故裁判例>住宅の買換えに要した費用と住宅改造費を認めた事例
⓵被害者は、本件事故当時に住んでいたマンションでは、介護に支障があったので、同マンションを売却して、一戸建ての住宅を購入したこと、⓶その買換えに、印紙代、移転登記費用、仲介手数料の合計209万2877円を要したこと、⓷購入した一戸建ての住宅の改造に960万円を要したことが認められる。被害者が一戸建ての住宅に買い換えたことには、その必要性があったものと認められるから、買換えに要した⓶の費用は、本件事故による損害と認められる。しかし、買い換えた住宅は、それ自体、その価格相当の資産価値を有するのであるから、買換えに要した代金までも、本件事故による損害と認めることはできない。⓷の費用には、必ずしも被害者の療養、介護のために必要でない費用が含まれていると認められるから、その60%に当たる576万円を本件事故による損害と認める。(被害者側は、一戸建ての購入費用5386万6027円から、マンションの売却代金から手数料を差し引いた残額1947万3150円を差し引いた3439万2877円を請求)
(横浜地裁平成23年5月27日判決)
<弁護士交通事故裁判例>自宅改造費用として1371万2390円を認めた事例
自宅改造費用:1371万2390円
被害者の症状、後遺障害の程度によれば、被害者らの自宅を改造してバリアフリー化する必要があると認められる。被害者らは、被害者ら5人が生活する自宅をバリアフリー化するための見積額は2742万4780円であるとしてハウスメーカー作成の設計書や見積書を提出する。しかしながら、上記文書を見ると、被害者ら自宅の1階および2階のいずれにもシステムキッチンを取り付けることや、食洗器、熱交換型換気扇、アコーディオンカーテン等の設置については、被害者を在宅介護するために必要不可欠な改造等とは認められないものもある上、自宅の改造により、同居の親族もまたその利便性を享受することが認められるから、本件事故と相当因果関係のある住宅改造費用としては上記見積額の5割に当たる1371万2390円を認めるのが相当である。
車両改造費:264万7331円
被害者ら使用車両にサイドリフトアップシートおよび電動車椅子収納装置の取付費用は86万1000円であり、福祉車両購入費と同型式車両の標準仕様車購入費との差額は24万7800円である。被害者の平均余命(40年)までの車両改造費の合計(6年ごとに6回買換え)は、264万7331円と認められる。
(東京地裁平成23年1月23日判決)
<弁護士交通事故裁判例>自宅改造費として1088万2648円を認めた事例
被害者は、日常生活全般にわたって全介護の状態にあったから、被害者の介護のために必要な設備を設置することを目的として自宅を改造する必要があることは明らかである。しかるに、被害者宅の改造工事の内容は、車椅子による生活を可能にするための工事、被害者に四肢体感麻痺の障害があり体温調節ができないことから行った工事、被害者のリハビリ用品を設置するための工事、被害者の介護のために訪問してくる訪問介護士らの作業を容易にするための工事であって、いずれも、必要合理的な内容ということができる。そして、その改造のために必要とされている費用に関しても、無用に高額であることを窺わせる事情も見当たらないことからすると、改造費用の全額が相当な損害と認められている(これらの工事により被害者の家族が利益を得ているといえるものも見当たらない。)。そして、被害者の死亡後、介護のための設備やウッドデッキと同様に、昇降機およびリハビリ用具を撤退することに伴い必要となった庭や家屋の原状回復費用も本件事故によって生じた損害ということができる。
(東京地裁平成22年2月12日判決)
<弁護士交通事故裁判例>車椅子仕様車購入費として普通車との差額を認めた事例
被害者は四肢の運動知覚の完全麻痺の後遺障害があり、その移動には車椅子の乗車が可能な自動車の必要性が認められる。証拠によれば、被害者は車椅子仕様車を購入したことが認められるが、当該車両は普通車をベースに車椅子仕様にしたものであり、その差額は60万1000円であると認められる。よって、60万1000円は本件事故と相当因果関係のある損害と認められる。
(名古屋地裁平成20年1月29日判決)
<弁護士交通事故裁判例>住宅改造費として介護仕様住宅と通常仕様住宅の建築費用の差額を認めた事例
住宅改造費:1065万7832円 (請求額:1270万4578円)
被害者は、後遺障害のため寝たきり状態であり、その日常生活のためには全面的介助が必要であり、そのためには自宅改造を要するが、現在
居住する住宅が県営住宅であり、改造は不可能である。被害者側提出の概算見積書を検討すると、介護仕様住宅においては、介護室の広さ高さが十分確保される必要は認められるものの、通常の住宅の建物規模と比較して著しく広大である必要は認められない。概算見積書の見積差額内訳書のうち建物規模を拡大したことによって生じる費用は差額工事費から除かれるのが相当である。住宅改造費は、介護仕様住宅の建築費用と通常仕様住宅の建築費用の差額である1065万7832円と認めるのが相当である。
車両改造費用:203万5698円 (請求額:203万5698円)
被害者の在宅介護生活における移動には、車両の改造が必要と認められ、介護仕様車両の価額と通常仕様車両の価額との差額については、本件事故と相当因果関係のある損害と認められる。症状固定までに1台、その後は耐用年数の6年ごとに平均余命55年間に9回買い替えが必要であるから、中間利息を6年ごとのライプニッツ係数で控除して203万5698円を認定する。
(名古屋地裁平成19年10月16日判決)
<弁護士交通事故裁判例>自動車購入費について平均余命間に8回交換を要すると認めた事例
自動車購入費:97万4384円 (請求額:135万6558円)
被害者は自宅療養開始後も1か月半に1度の頻度で通院するなどして自動車を使用し、車椅子に乗りながら公共交通機関を使用するには困難を伴うと考えられることから、特別仕様部分相当額の購入費(32万4600円)は必要かつ相当な損害と認められる。耐用年数8年として被害者の平均余命64年間に8回の交換を要するとして合計97万4384円となる。
介護器具購入費:760万5113円 (請求額:1446万7884円)
将来分の購入費については、公的扶助を受けられると認めるに足りる証拠はないから、考慮するのは相当ではない。
家屋改造費:572万7955円 (請求額:1848万3003円)
被害者の介護を行う上で、工事の全てが必要であったとは認められず、また、同居する家族も部分的に享受し得るので総工事費用の約3割の限度で必要かつ相当な損害と認めるのが相当である。
(大阪地裁平成19年2月21日判決)
<弁護士交通事故裁判例>福祉車両購入・買替費用を新車購入額の50%で認めた事例
被害者側が請求している福祉車両の購入費用およびその買替費用は、新車1台の購入金額を基礎とするものであるが、自動車としての利便性については、被害者側家族もその利益を享受するのであり、そのすべてを加害者側の負担とするのは相当ではない。そこで、加害者側の負担すべき割合は50%とするのが相当であり、本判決において、損害と認める金額は被害者側の請求にかかる新車購入費用の50%の金額を基礎として算出する。また、その耐用年数について、被害者側は8年と主張するが10年とするのが相当であり、将来の買替にかかる費用は、耐用年数を10年として算出する。
(大阪地裁平成17年9月27日判決)
<弁護士交通事故裁判例>家屋改造費等を将来の設備交換費用も含め認めた事例
家屋改造費:841万9000円 (請求額:841万9000円)
被害者は、後遺障害により、既存の自宅では生活できなかったため、平成15年9月に、自宅の敷地に身体障害者用居室を新たに増築したこと、その際、同居室に、被害者のために必要な身体障害者用のトイレ、浴室、天井走行リフト、車椅子用段差昇降機、電動シャッター、換気扇等の交換設備など特別な設備を設置したこと、これらの設備の設置に要した費用は841万9000円であったことが認められる。
将来の交換費用:166万3000円 (請求額:166万3000円)
(1)身体障害者用トイレに設置されたウレタン製台座の単価は7万2000円であり、5年ごとに交換する必要があると認められる。被害者の症状固定日の平均余命である56年間に5年ごと11回の交換が必要であり、ライプニッツ方式により中間利息を控除して得た現価額の合計は23万9000円となる。
(2)電動シャッターの単価および換気扇等の交換設備の価格の合計は302万6580円であって、いずれも20年ごとに交換の必要があると認められる。上記56年間に20年ごと2回の交換が必要であり、ライプニッツ方式により中間利息を控除して得た現価額の合計は142万4000円となる。
(さいたま地裁平成17年6月17日判決)
<弁護士交通事故裁判例>障害者用車両と住宅改造費を認めた事例
住宅改造費:1103万6340円
被害者は、重大な後遺障害を負っており、基本的日常行為ですら一人では満足に行うことができず、車椅子の生活を余儀なくされ、常時、介助者の介護を必要とせざるを得なくなってしまったこと、このため車椅子で移動を容易にするために床部分を補強し、玄関、台所、トイレ等を全面的に改造する必要が生じたものと認められる。もっとも、被害者のためのみならず、家族の利便性の向上性の向上部分もあるものと考えられるので、そのうち6割相当を損害と認める。
車両購入費:569万148円
被害者をリハビリのため毎日病院に連れていくために障害者用車両が不可欠であること、この車両1台購入には316万7000円が必要で、8年毎に新車に買換えなければならず、平均余命45年につき、8年毎のライプニッツ係数によりその原価を計算する。
(東京地裁平成16年12月21日判決)
« Older Entries Newer Entries »