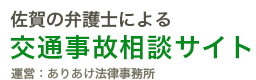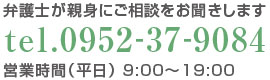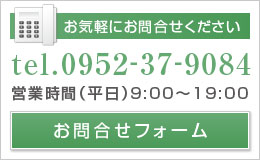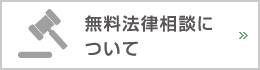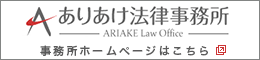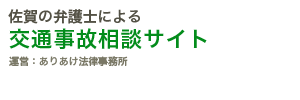Archive for the ‘未分類’ Category
<弁護士交通事故裁判例>将来の歩行補助器具代を認定した事例
被害者は、平成7年1月までは、歩行のために歩行補助器具を必要とし、それ以降も、アキレス腱が固まらないようにするために右器具を必要としている。
平成7年当時の歩行補助器具代は4万5451円であるところ、10歳から19歳までの9年間は、身体の成長に合わせて毎年右器具を作り替える必要があることから、1年に1度の割合でこれを購入するものし、ライプニッツ係数を用いて認定
20歳から平均余命である70年間は、5年に1度の割合で購入するものとしてライプニッツ係数を用いて認定
(東京地裁平成8年5月9日判決)
<弁護士交通事故裁判例>パソコンを購入する費用を損害と認めた事例
被害者は、イエス・ノーの応答が少し出来るレベルであり、その応答についてパソコンを使用することが意識水準の賊活ひいては知的水準の賊活への手掛かりになるとの医師の勧めにより82万7484円でパソコンおよびその周辺機器を購入したことが認められる。その耐用年数は10年とするのが相当であるから、症状固定時から平均余命までの55年間にわたり、10年に1台の割合で購入するとして、その費用につき年5%の中間利息の控除をライプニッツ法により計算し、次の金額を損害と認める。
(東京地裁平成7年7月27日判決)
<弁護士交通事故裁判例>平均余命までの10回の義足購入費を認めた事例
義足購入費 335万450円 (請求:589万7103円)
被害者の大腿の断端は非常に短く、通常の吸着式の義足は装着が出来ず、腰に補助ベルトを着けた吸着式の義足を必要とすること、その耐用年数は長くみても5年であり、被害者の余命から10回交換を必要とすること、義足は当初、91万4067円であったが、2回目からは57万181円で入手が可能であることが認められ、症状固定が事故後ほぼ1年経過していたことを考慮のうえ、ホフマン式計算法による年5分の中間利息を控除して義足費用の現価を算定する。
(大阪地裁平成7年3月22日判決)
<弁護士交通事故裁判例>将来の歯科補綴治療費を認めた事例
将来の歯科補綴費用 69万3490円 (被害者側主張どおり)
被害者の歯科補綴は一般には6、7年もつ程度のものであり、今後少なくともあと2回は歯科補綴治療を受ける必要があり、その1回の費用は70万円を下ることはなく、その各現価の合計は69万3490円を下回ることはない。
(横浜地裁平成5年12月16日判決)
<弁護士交通事故裁判例>人工呼吸器等の購入費用を定期金として認めた事例
既払分 肯定
寝具購入費 14万9350円(被害者側請求どおり)
人工呼吸器関係費 66万4306円(被害者側請求どおり)
頸椎固定器具購入費 2万4430円(被害者側請求どおり)
将来分 肯定
人工呼吸器付属品代 12万円(1台分)
頸椎固定器具 2万5000円(1台分)
車椅子 10万円(1台分)
呼吸器は5年、頸椎固定器具は6か月、車椅子は3年の耐用年数があることが認められ、これらの医療器具については将来にわたり、被害者が購入しなければならないものと認定される。
なお、被害者は将来の装具・器具等の購入費については定期金として請求した。裁判所はこの請求に対し、将来の損害につき一時の支払い請求としてこれを認める方法が一般的であるが、このことは必要な額につき定期金として支払い請求をすることができないことを意味するものではなく、被害者がかかる方法を選択した場合であって、将来の給付を求める訴えとしてあらかじめその請求をする必要性が認められるときには、これを認めることができるとして、将来の損害につき定期金給付を認めた。
(大阪地裁平成5年2月22日判決)
<弁護士交通事故裁判例>足関節の免荷装具代を平均余命48年分認めた事例
装具代 12万8400円 松葉杖・免荷装具代(被害者側主張どおり)
将来の免荷装具代 34万8340円 (被害者側主張額 43万3040円)
免荷装具の費用は1回につき6万750円、耐用年数は3年、購入回数は29歳男子の平均余命である48年間で16回とするのが相当である。
そこで、右購入費用の現価をライプニッツ方式で算出すると前記額となる。
(東京地裁平成4年9月11日判決)
<弁護士交通事故裁判例>被害者の平均余命間にわたる車椅子購入費を認めた事例
被害者の治療経過、後遺障害の内容程度、現在の状態に加えて、被害者が移動するためには車椅子が必要で、実際現在においても手押し式の普通型車椅子を購入して使用していること、麻痺レベルからして電動式車椅子が必要であると医師も判断していること、電動式車椅子の価格は、1台32万6500円程度であること、障害福祉法に基づく厚生省の基準によると、電動式でない普通の車椅子の耐用年数として4年、電動式車椅子の耐用年数として5年を予定していることが認められ、以上によれば、被害者は平均余命期間である58年間に少なくとも11台を購入する必要があり、うち2台については既に普通型車椅子を購入して使用しており、以後にさらに次のものを5年おきに購入する必要があり、その時には電動式車椅子が必要とされることが推認されるから、以上を基礎として、ホフマン式計算法により年5分の割合による中間利息を控除して、原価を算出すると、次のとおり143万9932円となる。
(大阪地裁平成3年10月29日判決)
<弁護士交通事故裁判例>将来の義歯代、顔面醜状に対する化粧品代を認めた事例
将来の義歯代 41万2669円(被害者側主張額 53万5499円)
義歯代は1回15万4500円であること、耐用年数7年毎に義歯の取替えが必要であり、被害者の平均余命の範囲内で5回取り替えるものとして、新ホフマン形式で原価を算定。
将来の化粧品代 52万2765円(被害者側主張額 165万8525円)
被害者は顔面の瘢痕形成術を行った昭和62年11月から昭和63年5月までの1年間は治療行為として着色過剰予防の目的で紫外線を遮断するために化粧品の使用が必要であったこと、その後は化粧により若干でも瘢痕を目立たなくすることが商社の営業マンとして職務上必要であること、17か月間に化粧品代として1万8100円を要したことが認められ、同額の2分の1、10年間の限度で相当因果関係を認めることができる。
(名古屋地裁平成3年1月25日判決)
<弁護士交通事故裁判例>下肢短縮の後遺障害につき将来の義足費用を認めた事例
大腿義足の製作費用は1本33万7500円、機能的にみて長くとも5年間の経過により制作しなおす必要があり、被害者の症状固定時の平均余命は51年であり、中途で破損等で使用不能となることがあり得ること、その間において少なくない修理費用も要することが認められる。そうすると、その損害額は右の諸事情に鑑み、修理費用等維持にかかる費用の請求がなされていないことも加味すると、4年に1度制作し直すとするのが合理的である。
(東京地裁昭和61年11月21日判決)
<弁護士交通事故裁判例>平均余命間3年に1度、車椅子の購入費用を認めた事例
被害者の後遺症に照らし、生涯、車椅子が必要であることが認められ、その車椅子は1台10万円であり、耐用年数が3年であることが認められる。
毎年10万円の3分の1ずつ支出するものとみなしホフマン係数により原価を算出
(東京高裁昭和60年12月25日判決)
« Older Entries Newer Entries »