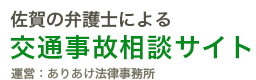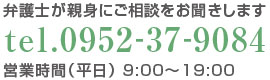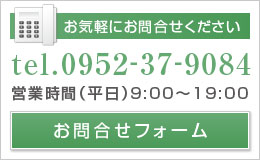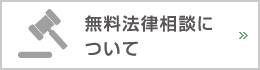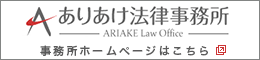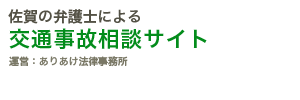Archive for the ‘未分類’ Category
<弁護士交通事故裁判例>将来介護費を月額40万円を相当と認めた事例
口頭弁論終結時まで,通所型介護サービスの利用負担額月額1万8542円および介護サービスの利用により妻の負担が軽減していることを考慮し,月額12万円で認定する。
妻による介護の内容としては,見守り,声掛けが中心であることのほか,介護サービス利用額の平均月額は,18万5422円であること,妻の年齢(68歳)等を皇后考慮し,被害者が平均余命である86歳になるまでの期間を通じ月額40万円とするのが相当である(介護保険適用による事故負担分と公費扶助分に関し,口頭弁論終結時以降の,金額が具体化していない将来の介護費用については,現在適用のある介護保険の給付内容や水準が将来においても維持されることが必ずしも確実とはいえないことから,介護保険からの給付を含めた介護費用の額を考慮することが相当とである。)。
(大阪地裁平成24年5月16日判決)
<弁護士交通事故裁判例>将来の介護費用について一時金賠償方式に変更した裁判例
損害保険会社の経営破綻の可能性もあり,定期金賠償方式では履行確保の不確実性があること,②定期金賠償方式では紛争の一回的解決が図れず,被害者と加害者の関係性が長期にわたり固定化することが耐え難いことを理由に被害者側は一時金賠償方式による支払いを求めており,また,被害者は在宅療法をしており,これを前提に損害を算定することが公平の理念に反するものということはできず,民訴法117条を勘案しても,被害者側の申立てに反して,定期金賠償方式を採用することは相当であるとは解されない。
(福岡高裁平成23年12月22日判決)
<弁護士交通事故裁判例>将来の介護費日額5000円で平均余命認めた事例
被害者は本件事故による後遺障害のために,住宅の改造をしてもなお,入浴については全介助が必要であり,衣類の脱着についてもボタンのあるものについては介助が必要であり,食事等一応自立とされる日常生活動作についても,不自由な左手で自助具を使用して何とか自立できるにとどまるから,随時介助が必要な状態に近いと認められる。これらの事情からすれば,現在週2回程度介護保険によりデイサービスを受け,入浴もさせてもらっていることを考慮しても,夫による被害者の介助費用として,日額5000円を認めるのが相当である。
(名古屋地裁平成23年10月14日判決)
<弁護士交通事故裁判例>将来介護費を日額4000円で平均余命まで認めた事例
被害者は,身体的な機能については特段支障はなく,身体的な介護をする必要性は認められない。しかし,高次脳機能障害により,人格変化が生じているため,日常生活をする上でも,見守りをする必要がある。介護の主たる内容は,自発性の低下した被害者に対し,入浴等の日常的に必要な行為のほぼ全般にわたって,それを必要な時ごとに促すことと,人格変化のために話がくどくなった被害者の話を聞いてやることなどであり,身体的な負担はあまりないことであるが,被害者の妻にとって精神的には相当な負担になるものと認められる。妻の年齢と持病があること等からすれば,週2回デイサービスの施設に通所するようになり,妻の負担が軽くなったこと,介護保険によってもっとデイサービスを受けることも可能であることを考慮しても,被害者の症状固定時からの平均余命20年にわたって,看視,見守りの介護料として日額4000円を認めウのが相当である。
(名古屋地裁平成23年9月16日判決)
<弁護士交通事故裁判例>将来の付添介護費を平均余命まで日額2万円で認めた事例
被害者の妻が67歳に達するまでの27年間は,近親者介護による介護体制が,それ以降被害者の平均余命まで(15年)は,職業介護人による介護体制が必要であると認められる。被害者の介護の費用の多くは,現在のところ公費でまかなわれていると認められるが,被害者が負担しなければならない費用もある。また,妻の負担は大きいものと考えられるうえ,妻が365日介護できるとも限らない。これらを考慮して,近親者介護による介護体制の間は,日額1万円を認める。職業付添人による介護体制の間は,被害者の症状等を甲考慮して日額2万円を認める。
(横浜地裁平成23年5月27日判決)
<弁護士交通事故裁判例>母親が67歳以降は職業介護(日額2万5000円)で認めた事例
母親が67歳になるまでの20年間,1年のうち300日間については日中の職業介護(日額2万円)と夜間の近親者介護(日額5000円),残りの65日官については全日の近親者介護(日額1万円)が行われるものとして認めるのが相当。
母親が67歳以降の37年間,職業人介護(日額1万5000円)を認めるのが相当。
(名古屋地裁平成23年2月18日判決)
<弁護士交通事故裁判例>母が67歳以降の将来介護費日額2万円で認めた事例
症状固定時から母が67歳に達するまでの15年間は,被害者の後遺障害の程度・内容から必要とされる介護の程度,母が就労を望んでいることより,週6日は10時間の訪問介護を受ける必要があり,1週間あたり10万2900円,母が担当する部分については,週6日の7時間半は日額3000円,週1回の17時間半は日額1万円とするのが妥当である。
母が67歳に達した後は,被害者の介護に要する時間は1日あたり17時間半と長時間であるので,職業介護人2人分の仕事であることを考慮すると,日額2万円と認めるのが相当である。
(名古屋地裁平成22年12月7日判決)
<弁護士交通事故裁判例>将来付添看護費につき妻が67歳以降は日額2万円で認めた事例
妻が67歳までは,妻が復帰すれば今よりも長い時間のヘルパー利用が不可避となること,今と同様の金額でのデイサービスの利用が今後も可能とは限らないこと,夜間,早朝は妻による近親者介護が必要であることにかんがみ,平日(年240日)は日額1万6000円,公休日(年125日)は日額9000円が相当であると認められる。
それ以降の平均余命期間,妻が67歳となった以降は,妻が被害者の介護を全くできなくなるとはいえないが,主として職業介護人による介護が行われる蓋然性が高いこと,現時点での職業介護人の1時間当たりの単価等を考慮し,上記期間の付添看護費は日額2万円が相当であると認められる。
(東京地裁平成22年10月27日判決)
<弁護士交通事故裁判例>母親が67歳以降付添介護費日額15000円で認めた事例
両親による介護可能な期間(母親が67歳まで)については,近親者付添費用は,被害者の後遺障害の程度によれば,1日8000円が相当である。
母親が68歳になった以降,被害者の平均余命の残期間は,両親の体力の減退により被害者の介護にあたるのは不可能であり,職業人介護を要すると認められるところ,被害者の後遺障害の程度によれば,被害者に対する介護は,随時の介護で足りるほか,介護器具を使用することなどを考慮すると,職業付添人費用は,1日1万5000円が相当である。
(さいたま地裁平成22年9月27日判決)
<弁護士交通事故裁判例>将来介護費について日額6000円で認めた事例
被害者には看視・声掛けのための付添看護が必要ということになるが,その費用額は,被害者の後遺障害の程度(身体動作的には排泄,食事等の活動を行うことはできるが,生命維持に必要な身辺動作については家族からの看視・声掛けが必要な状態と認められる。)等の諸事情を考慮して,1日当たり6000円をもって相当と認める。
(大阪地裁平成22年5月25日判決)
« Older Entries Newer Entries »