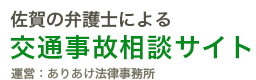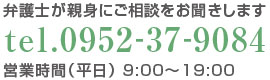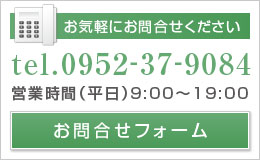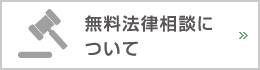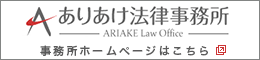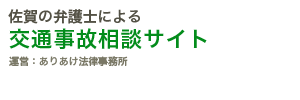Archive for the ‘未分類’ Category
<弁護士交通事故裁判例>飲食店経営の代表取締役の休業損害につき、役員報酬のうち70%を労務の対価と認定した事例
生活態様:ラーメン店を経営する有限会社の代表取締役
有限会社は事実上、被害者と妻が経営しており、被害者はラーメン店を、
妻は中華料理店を事実上経営していた。被害者はラーメン店を年中無休の
24時間で経営し、被害者と従業員5人が勤務していた。被害者は、常時
午後10時から翌日お午後2時まで勤務し、従業員と同じ仕事をしていたが、
醤油ベースだけは被害者が作成していた。
算定基礎:年収¥7,140,000
被害者の役員報酬のうち70%に相当する金額
休業日数:104日×0.8+120日×0.5+142日×0.3
平成7年1月末までの104日は平均して80%、平成7年2月1日から
平成7年5月末までの120日は平均して50%、平成7年6月1日から
平成7年10月20日までの142日は平均して30%労働能力が低下した
状態であったと認められる。
認容額:¥3,634,553
(東京地裁 平成10年7月29日判決)
<弁護士交通事故裁判例>コンピューターソフト会社の代表取締役の休業損害について、賃金センサスで認定した事例
生活態様:コンピューターソフト会社の代表取締役
役員報酬の支給を受けているが、従業員と同じようにコンピューター・
ソフトの設計等に従事していた。
算定基礎:年収¥6,490,300
(H6賃金センサス・産業別・企業規模計・学歴計40~44歳男子
平均給与)
休業日数:14日
本件事故によって受けた損害の程度はそれほど大きなものではなかった
と認められるものの、事故後2週間程度の休業はやむを得なかったもの
と認められる。
認容額 :¥248,943
(大阪地裁 平成9年3月27日判決)
<弁護士交通事故裁判例>同族会社の代表者の休業損害につき、事故当日から2ヶ月間は100%、その後の11ヶ月間は50%とした事例
生活態様:同族会社の代表者
算定基礎:年収¥4,800,000
事故前は役員報酬として¥4,800,000が支給されていたが、事故後は支給が
なかったこと、会社の売上がH3年度が約¥19,120,000、H4年度が
¥10,650,000と受傷後半減していること、H4の賃金センサス50歳平均
賃金等を総合考慮すると、少なくとも¥4,800,000の年収を得ていたと認め
るのが相当である。
休業日数:232日
H5.6.3まで入通院治療を要したこと、その間、殆ど就労していなかったことが
認められ、右通院治療状況、通院実日数、H4.7初めから軽作業に従業することが
可能との医師の所見などを総合考慮すると、H4.6末日までは100%、H4.7
初めからH5.6.3まで平均して50%労働能力に制約があったと認めるのが相当
である。
認容額 :¥3,050,958
(大阪地裁 平成6年8月26日判決)
<弁護士交通事故裁判例>代表取締役に給与を立替払いした会社からの損害賠償請求を認めた事例
生活態様:資本金¥1,000,000のプラスチック包装品等の製造販売等を目的
とする会社(従業員10名)の代表取締役
被害者は株式を全て所有し,同社の業務全般を統括するほか技術面の最高
責任者として金型の設計や工場の点検・監督,得意先との交渉にあたり,
かつ工場に常勤して従業員と同様の部品製造の仕事も担当していた。
算定基礎:年額¥6,480,000
会社からの年額¥7,200,000の給与のうち,労務対価部分は会社の
実態と被害者の役割等に鑑みて支払額の9割とみるべきである。
休業日数:23日(事故当日から病院への最終通院日まで。)
認容額 :¥408,328
(東京地裁 平成6年3月25日判決)
<弁護士交通事故裁判例>2会社,1商店経営の代表取締役について,各々の役員報酬ではなく,事故前後の確定申告書における所得額により算定した事例
生活態様:旅館営業会社,不動産業売買・仲介および健康マット仕入,委託販売会社の
代表取締役のほか,鞄の卸業も営んでいた。
算定基礎:年額¥5,462,625
被害者の3つの営業による所得(不動産収入を除く)は,確定申告書に
よると,S58年分は¥9,368,117であるが,S59年分は
途中で事故に遭ったため¥8,209,688,S60年分は
¥3,905,492である。よって事故による減収額は,S59年分と
S58年分との差額¥1,158,429およびS60年以降は,S58
年分からS60年分を差し引いた額¥5,462,625とするのが
相当である。(役員報酬の事故後の減額分月額¥800,000が基礎
との被害者主張を採用せず。)
休業日数:1221日間(S59.9.3~S63.1.6)
認容額 :¥17,546,304
(S59年分)¥1,158,429
(S60年以降3年分)1年につき¥5,462,625
(東京地裁 平成5年7月30日判決)
<弁護士交通事故裁判例>役員報酬という名称であっても,実体は全額が労働の対価としての性格をもつとして,その全額を基礎とした事例
生活態様:アルミサッシ,シャッター,エクステリア製品の販売およびこれら取付け
工事の請負業を営む授業因9名(身内の兄弟を含む。)の会社の代表取締役
で,1か月¥530,000の給与を得ていた。
算定基礎:月収¥530,000
・被害者は仕入,販売,受注および施行を行い,8割は現場での仕事
・役員といえども,欠勤日数は日割り計算し給与から控除される。
・被害者の兄弟(役員ではない)の年収額は,被害者の年収額とほぼ同額
・税務上も給与所得として処理。利益配当は給与とは別に処理
これら事実に照らすと,被害者に対する給与は,これが役員報酬なる名称
が使用されているとしても,その実態は労働の対価としての性格をもつもの
であって,利益配当分等の性質をもつ部分は含まれていないと認めるのが
相当である。
休業日数:74日間(H1.2.23~5.7)
認容額 :¥1,280,834
上記欠勤期間中,会社より支給を受けることができなかった実額を認定
(名古屋地裁 平成2年8月10日判決)
<弁護士交通事故裁判例>会社役員の休業損害について、役員報酬月額¥1,000,000のうち6割を労務の対価としての実質をもつとして算定した事例
生活態様:ダイカスト製造販売を生業とする資本金¥10,000,000、従業員40名の会社
代表取締役で、業務全般を統括するほか、技術面の最高責任者として金型設計、工場の
点検監視、得意先の訪問打合せ等の業務に従事
算定基礎:月額¥600,000
会社役員の報酬については、利益配分等の実質をもつ部分と労務の対価としての実質を
持つ部分との両社があり、前者は解雇される等の事情がない限り損害は発生しないが、
後者は事故により労務を提供できなくなった場合、休業損害の問題が生じるものと解す
べき。被害者は従業員としての実質的活動も行っており、会社規模、業務内容と被害者
の担当職務等を総合勘定すると、報酬月額¥1,000,000のうち¥600,000
が労務の対価としての実質をもつ部分と認めるのが相当
休業日数:S58.3.9~6.15は100%
S58.6.16~S59.3は80%
S59.4~12は50%、S60.1~5は20%
認容額 :¥9,805,161
(千葉地裁 昭和61年10月29日判決)
<弁護士交通事故裁判例>報酬につき、会社が肩代わりしたものとして加害者に対し求償・償還請求できるとした事例
生活態様:被害者の会社は工作機械部品の製作・販売を業とする有限会社で、被害者が個人で営んでいたものを昭和48年に会社組織にしたもの。事故当時は被害者 と被害者の長男とアルバイト1名の計3名が稼働し、被害者は加工、組立等の現業のほか、受注、集金、経理等もしているなど、被害者の個人会社という
べき実態であった。
算定基礎:年収¥3,600,000(1か月¥300,000)
被害者は事故前、会社から年収¥3,600,000(1か月¥300,000)の報酬を得ていたが、それは労務の対価である賃金というべきもの
休業日数:治療16か月間のうち、当初6か月間100%、次の6か月間70%、残りの4か月40%の就労不能ないし制限があったと推認通院期間中は、次第に
症状が軽快していったものと認めるのが経験則に合致し、その間事務的仕事には従事し得た。
認容額: ¥3,540,000
被害者が休業損害として加害者に請求できるものを会社が肩代りして支払ったものの求償ないし償還請求であり、弁済者の任意代位あるいは事務管理の
法理を類推適用して認めるのが相当
(東京地裁 昭和58年7月25日判決)
<弁護士交通事故裁判例>主婦の休業損害について賃金センサス女性学歴計全年齢を基礎に認めた事例
生活態様:夫の経営する会計事務所に勤務する兼業主婦
算定基礎:年額¥3,468,800
平成19年当時の会計事務所における所得は、女性の賃金センサス年収額に比し定額であるため、基礎収入は平成19年賃金センサス女性学歴計全年齢
を相当と認める。
休業日数:382日×80%
症状の経過および程度に照らし、症状固定までの通院日数382日、収入相当額の80%について休業損害が生じたと認めるのが相当である。
認容額: ¥2,904,288
(東京地裁 平成26年11月17日判決)
<弁護士交通事故裁判例>31歳女子の休業損害について入院が終了するまでは100%、その後症状固定日までは80%で認めた事例
生活態様:本件事故当時夫と長女(生後8か月)の3人家族で、家事をするかたわら、義父の経営する建設会社で、一定の経理事務を担当し、月¥120,000 前後の支給を受けていた。
算定基礎:年額¥3,432,500
平成18年賃金センサス産業計・学歴計・企業規模計女性労働者全年齢平均賃金
休業日数:27か月
本件事故当時から症状固定日である平成21年1月9日までの2年6か月休業したことが認められるが、被害者は、退院してからは、夫の扶助を受けなが らも、自宅で一定の家事に従事していたものと考えられるから、遅くとも、3度の入院治療が終了したのちである平成19年10月から症状固定までの
1年3か月間は、一定程度の労働能力を有していたものと認められる。本件に現れた諸般の事情に鑑みると、労働能力の喪失割合は80%と認める。
認容額: ¥7,723,123
(大阪地裁 平成23年3月11日判決)
« Older Entries Newer Entries »