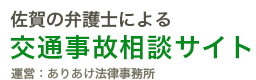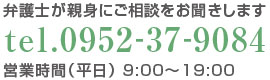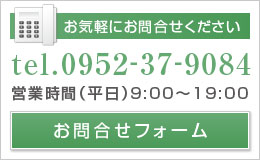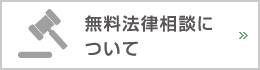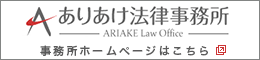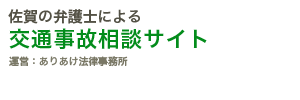Archive for the ‘未分類’ Category
<弁護士交通事故裁判例>休業損害についてアルバイト収入をもとに認めた事例
生活態様:被害者は、本件事故当時高校3年生で、ファーストフード店でアルバイト勤務していた。
算定基礎:H25.11.5~H5.12.10まで予定されていた勤務を欠勤し、その休業損害は10万3970円であると認めるのが相当である。(休業損害証明書起債額)。
休業日数:26日
認容額:10万3970円
(名古屋地裁平成25年1月24日判決)
<弁護士交通事故裁判例>マンション賃料差額と転居費用を認めた事例
賃貸差額・転居費用:725万2218円
被害者の父親は、本件事故当時、非バリアフリーの賃貸マンション(賃料月額16万3000円)に居住していたが、H24.3.15、被害者の在宅介護を行うため、バリアフリーの賃貸マンション(期間をH26.3.31までとする定期建物賃貸借。賃料月額20万円)に転居したこと(1回目の転居)、H26.2.26、肩書住所地所在のバリアフリーの賃貸マンション(賃料月額23万5000円)に転居したこと(2回目の転居)、転居費用は1回目20万4750円、2回目20万円であることが認められる。被害者の後遺障害の内容、程度等に照らすと、転居の必要性は否定し得ないものの、2回目の転居と本件事故との間に相当因果関係があるとまで認めるのは困難である。また、上記の各マンションは、間取りも異なる上、立地条件も異なるのであって、単に賃料に差異があることのみから賃料差額を本件事故と因果関係のある損害というのは困難である。シニア向けの分譲マンションは、同じ面積でも、一般の分譲マンションに比し、販売価格が2割程度高くなるとの指摘があることなどを総合考慮すると、本件事故と相当因果関係のある賃料差額相当分の損害は月額3万円とするのが相当である。本件事故と相当因果関係のある賃料差額は704万7468円(3万円×12か月×19.5763(ライプニッツ係数))、転居費用は20万4750円とするのが相当である。
(東京地裁平成28年2月25日判決)
<弁護士交通事故裁判例>被害者の成年後人報酬等を損害と認めた事例
後見申立費用:5870円
被害者は、後見申立費用として5870円を要したことが認められ、本件事故と相当因果関係にある損害と認められる。
後見人報酬:318万5192円
証拠によれば、成年後見人の基本報酬額は、家庭裁判所が裁量により審判で決定すること、管理財産が5000万円を超える場合のめやすとなる金額は月額5~6万円であることが認められる。被害者が加害者から損害賠償金の支払いを受けた場合には、被害者の財産の総額が5000万円を超えることが見込まれる。他方で、成年後見人の報酬はあくまでも家庭裁判所が裁量により決定するものであることや、被害者について後見制度支援信託の利用が想定され、成年後見人自身が被害者の財産のすべてを管理するとは考えられないことに照らすと、成年後見人の報酬として将来にわたり6万円を要するとは認められないが、少なくとも月額2万円を要すると認められる。被害者についてH25.10.16の後見開始から、症状固定時を基準として中間利息を控除して次のとおりとなる。
2万円×10月×0.9070+2万×12月×(14.3752-1.8594)=318万5192円
(大阪地裁平成27年9月4日判決)
<弁護士交通事故裁判例>被害者の妻の犬のペットホテル費用を損害と認めた事例
ペットホテル代:1万8900円
被害者の妻の飼う犬がH24.5.4から同5.8までペットホテルに預けられ、そのための費用として1万8900円が支出された事実が認められる。同ペットホテルを利用したのは、被害者の葬儀等に対応するためであると推認でき、その期間としても4~5日間は相当といえることからすれば、上記金額は本件事故と相当因果関係のある損害と認められる。
刑事事件公判費用:0円
被害者の妻子が刑事公判に被害者として参加するか否かは、彼らの意向等により定まるものであり、事故により通常生じるとは言い難いから、刑事公判に参加するための費用を、本件事故と因果関係のある損害と認めることはできない。
東京ディズニーランドチケット代:0円
同チケットがH25.5.1(本件事故の1年後)まで有効だったことからすれば、同チケット代は、本件事故と相当因果関係のある損害と認めることはできない。
(大阪地裁平成27年1月16日判決)
<弁護士交通事故裁判例>費用について被害者側に不利益に扱うべきではないとした事例
弁護士費用:
加害者は、被害者側が自賠責保険に被害者請求をすることで賠償金3000万円を回収をできたはずであるのにしなかったのであるから、弁護士費用の算定に当たっては、この分を控除すべきである旨主張する。しかしながら、自賠責の被害者請求は、被害者の救済のために設けられた制度であって、その行使が義務付けられているものではないから、これを利用しなかったからといって、そのことを不利益に扱うべきものではなく、加害者の主張は採用できない。
※認容額 被害者の妻:550万円(弁護士費用を除く損害額5549万4268円) 被害者の子:290万円(弁護士費用を除く損害額2919万5585円) 被害者の母:5万円(弁護士費用を除く損害額45万円)
(さいたま地裁平成26年12月19日判決)
<弁護士交通事故裁判例>被害者の介護給付と自己負担相当額を認めた事例
施設料:742万8202円(H22.6.26~H24.7.31)
被害者の症状固定後の心身の状況に照らして、施設入所は必要有益であったと認められ、これに要した介護給付相当額と被害者の自己負担相当額は本件事故と相当因果関係のある損害に当たるというべきである。被害者の自己負担分のうちには、食費、日用品費、教養娯楽費、床屋代、洗濯代が含まれており、これらは施設利用の有無にかかわらず必要になる費用であるから、これを控除するのが相当である。(25か月分114万8975円)。施設介護を利用した約2年間の自己負担相当額の損害は以下の計算式のとおり、97万4942円となる。
(224万1333円-114万8975円)×12/25×1.8594=97万4942円
同様に施設介護を利用した約2年間の介護給付相当額の損害は以下の計算式のとおり、645万3260円となる。
723万447円×12/25×1.8594=645万3260円
したがって、本件事故と相当因果関係のある施設料相当の損害は、合計742万8202円となる。
(東京地裁平成26年11月27日判決)
<弁護士交通事故裁判例>67歳被害者の成年後見費用を認めた事例
成年後見費用:559万7407円
被害者は、本件事故で受けた傷害により意思能力を喪失し、本件訴訟の提起等のため、成年後見人の選任を余儀なくされ、H21.12.2、京都家庭裁判所で成年後見開始決定を受けたこと、その際、同裁判所は、司法書士を成年後見人に選任したが、その基本報酬として、H22.7までの約8か月は月額2万円、自賠責保険からの支払いがあったH22.8以降は月額4万円を要し、このほかに事務費として年額3万円を要することが認められる。証拠には、上記のほか、付加報酬に関する記載もあるが、この部分については、相当な報酬額を算定するに足る的確な証拠がない。被害者は、症状固定時の年齢は67歳で、その時点での平均余命は約17年であるところ、以上によれば、①症状固定後の1年間に35万円を要し、②その後16年間は毎年少なくとも51万円を要するものと推認されるから、その総額は、以下の計算式により559万7407円となる。①35万円×0.9524=33万3340円 ②51万×(11.2741-0.9524)=526万4067円 ①+②=559万7407円
<弁護士交通事故裁判例>成年後見人申立てのための弁護士費用等を認めた事例
成年後見申立費用:15万6000円
被害者が本件事故によって受傷したことにより、被害者の子は成年後見申立てを余儀なくされたから、本件事故と相当因果関係のある損害といえる。そして、成年後見申立てに当たっては、一定額の収入印紙や切手代、本人や成年後見人候補者の戸籍謄本および住民票等が必要となることは当裁判所に顕著な事実である上、弁護士に依頼して家庭裁判所への成年後見申立手続をとったと認められることからすれば、被害者主張の弁護士費用および実費の合計額15万6000円をもって被害者に生じた損害と認める。
(大阪地裁平成26年6月26日判決)
<弁護士交通事故裁判例>家賃相当額の70%を認めた事例
家賃相当額:1251万6000円
被害者は,平成23年11月15日(当時80歳)以降介護施設に入居していること,入居一時金として,家賃相当額の1788万円(3840万円×2回+1020万円)を支出したことが認められる。食費や水道光熱費は本件事故に遭わなくても生活に必要な費用であり,住居費も同様である。もっとも,被害者は,本件事故に遭わなければ自宅に居住することができたにもかかわらず,介護施設の整った施設での生活を余儀なくされたのであり,本来必要な額を大きく超える住居費が必要になったことは否定できない。家賃相当額1788万円の70%の限度で認めるのが相当である。
※将来介護費の中に含めての認定。
(神戸地裁平成26年4月30日判決)
<弁護士交通事故裁判例>刑事記録謄写費用を損害と認めた事例
被害者側は,本件事故の原因を知るために,刑事記録を謄写し,その費用として6600円を支払ったことが認められるところ,これは,本件事故と相当因果関係のある損害と認められる。したがって,文書料については,当事者間に争いのない400円に6600円を加えた7060円であると認められる。
(さいたま地裁平成26年3月31日判決)
« Older Entries Newer Entries »